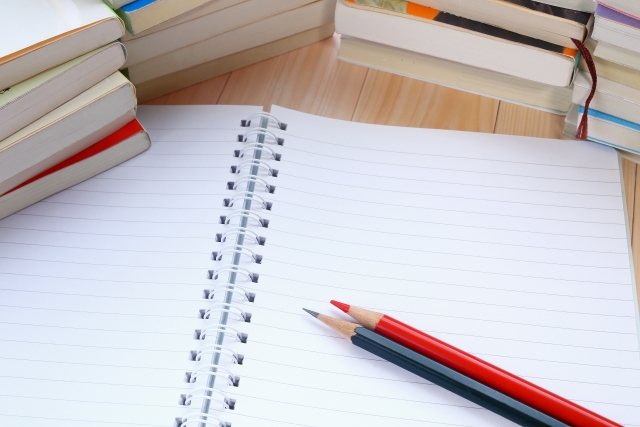こんにちは、真和ブログへようこそ!
3月といえば「春分の日」。春分の日には「ぼたもち」を食べる習慣がありますが、なぜ春のお彼岸にはぼたもちを食べるのでしょうか?今日は、その由来についてお話しします!
ぼたもちとおはぎの違いって?
春分の日には「ぼたもち」、秋分の日には「おはぎ」を食べるのが一般的ですが、実はこの二つ、ほぼ同じ食べ物です。どちらももち米とうるち米を混ぜたものを丸め、あんこで包んだ和菓子です。
違いは名前の由来にあります。
- 春:「牡丹(ぼたん)」の花にちなんで「ぼたもち」
- 秋:「萩(はぎ)」の花にちなんで「おはぎ」
また、昔は春はこしあん、秋は粒あんを使うことが多かったそうです。これは、小豆の収穫時期が秋で、新鮮な小豆の皮ごと使えるため「粒あん」、時間が経つと皮が硬くなるため春には「こしあん」を使ったと言われています。
なぜお彼岸にぼたもちを食べるの?
お彼岸にぼたもちを食べる習慣には、いくつかの説があります。
-
小豆の赤色には魔除けの力がある
昔から赤い色には邪気を払う力があると信じられており、ご先祖様への供え物としてぼたもちが選ばれたそうです。 -
エネルギー源としてのもち米
昔の人にとって、もち米は貴重な食べ物。お彼岸には労働を休み、体力をつけるためにも、栄養価の高いぼたもちが食べられていたとされています。
今年の春分の日は「ぼたもち」を味わおう!
春分の日は、昼と夜の長さがほぼ同じになる特別な日。そして、お彼岸はご先祖様を敬う大切な時期です。今年の春分の日には、昔ながらの習慣を楽しみながら、ぼたもちを味わってみるのも良いかもしれませんね。
今回の真和ブログはここまでです。足の爪でお困りの方は、当院にお気軽にご相談下さい。